この投稿では、ヴィルヘルム・バックハウスによる1953年のブラームスのピアノ協奏曲第1番の録音に焦点を当てています。モノラル録音でありながら、バックハウスの独特なロマンティックさと技術が際立ち、指揮者カール・ベームとの協演が印象的です。音質は現代に比べると劣りますが、一聴する価値がある名演奏と評価されています。
オトマール・スウィトナーとシュターツカペレ・ベルリンによるブルックナー交響曲第7番の録音が、1989年1月にベルリンで行われ、最新のマスタリングが施されたタワーレコード限定CDとして紹介されている。この演奏は軽やかさと気品に満ち、特に第1楽章と第2楽章の繊細な響きが高く評価されている。若葉の緑が映える季節にぴったりの音楽として推奨される。
約2ヶ月ぶりの投稿で、クラシック音楽からしばらく離れていたことを振り返りつつ、オトマール・スウィトナーによるブルックナーの交響曲第1番を紹介します。スウィトナーは東ドイツを代表する指揮者で、彼の録音はリンツ稿を使用し、特徴的な素朴さが表れています。彼の指揮のもと、演奏は透明感あり、ブルックナーの魅力を引き出しています。
指揮者セルジュ・チェリビダッケはベートーヴェンの第九をほとんど指揮しない。書籍によると、第4楽章を「サラダ」とし、無秩序を嫌ったと言う。また、ヴィルヘルム・フルトヴェングラーの影響も指揮回避の理由とされる。彼の第九は1989年の記録が唯一で、評価は分かれる。
マリス・ヤンソンスは1979年から2002年までオスロ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者として活躍し、世界的なオーケストラに育て上げた。1992年に録音されたドヴォルザークの交響曲第7番と第8番は、彼の卓越した演奏技術を示しており、特に第7番は感動を呼ぶ名演となっている。
オランダのロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団と名指揮者カール・ベームの意外なコラボレーション。コンセルトヘボウでの演奏会に13回しか指揮していませんが1955年にモーツァルトの交響曲5曲を録音しています。厳格な演奏で意外な組み合わせだからこその魅力があります。
スヴャトスラフ・リヒテルのシューベルトの『さすらい人幻想曲』を特に愛していた。リヒテルはこの曲を「導きの星」と称し、1963年にパリでの演奏で新たな一面を引き出しました。演奏には強靭さと繊細さが融合し、大胆で表情が豊か。そんなリヒテルのさすらい人幻想曲を紹介します。











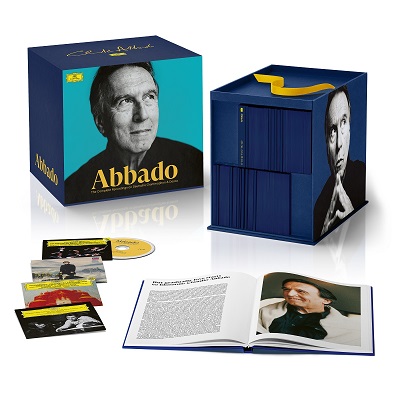





最近のコメント