
このアルバムの3つのポイント
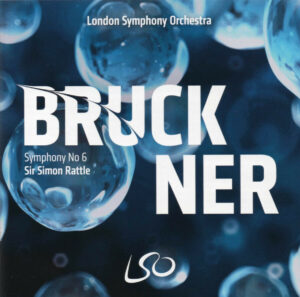
- サイモン・ラトルとロンドン響のブルックナー・チクルス第1弾
- 2015年に出版されたばかりのコールス版を使用した
- 従来のブルックナー像にとらわれないまろやかさとしなやかさ
最近注目が集まるブルックナーの第6番
ブルックナーの交響曲の中で、人気の2つの交響曲、第5番と第7番の間に存在するのが第6番。対位法の集大成となった荘厳な第5番、そして巨大で深遠なアダージョがある第7番に比べると、地味なこの第6番はイ長調の交響曲で、「舞踏の神化」とヴァーグナーが称賛したベートーヴェンの交響曲第7番と同じ調性。ブルックナーの6番もリズムに特徴があります。近年になって評価されるようになってきたことに伴い、録音も増えてきました。
最新の研究を取り入れたラトルの活躍
イギリス出身のサー・サイモン・ラトルは現代の音楽学者による最新の研究を踏まえて補筆版や新しい校訂版を使うことが多い指揮者です。
ベートーヴェンではベーレンライター社の新しい校訂版を使った交響曲全集、マーラーは第5楽章までの補筆版を使った交響曲第10番、ホルストの「惑星」では当時惑星の一つだった「冥王星」を含んだ組曲、さらにブルックナーも交響曲第9番の第4楽章を補筆したものを演奏、録音し、2012年にベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と世界初演しています。これはニコラ・サマーレ (Nicola Samale)、ジョン・フィリップス (John Phillips)、ベンヤミン=グンナー・コールス (Benjamin-Gunnar Cohrs)、ジュゼッペ・マッツーカ (Giuseppe Mazzuca)の4人の音楽研究家による何度もの改訂経てついに2012年に完成した演奏用完成版 (サマーレ・フィリップス・コールス・マッツーカ編)を使用しました。
コールス版(2015年)による第6番演奏
今回のラトルとロンドン交響楽団によるブルックナー・チクルスでも、コールスが校訂したものを使っており、第6番は2015年に発表したコールス版原典版を使用しています。
ラトルと言えばドイツ=オーストリア音楽を「所有していない」イギリス出身だからこその革新的な解釈で、ベートーヴェンやブラームス、マーラーなどでもこれまでの伝統にとらわれない、大胆なテンポ・ルバートやアゴーギクでの演奏が特徴的でした。
ただ、このブルックナーの第6番をはじめから聴くとラトルにしてはやけにおとなしいという印象。やや早めのテンポで駆けていきますが、冒頭のヴァイオリンのユニークなリズムのフレーズも特に強調することもなく、その後にティンパニや弦のトゥッティで引き継がれるこのリズムもあまり目立たせません。他の指揮者、例えばセルジュ・チェリビダッケやマリス・ヤンソンス、クリスティアン・ティーレマンなどはこのリズムを際立たせていましたし、往年のオットー・クレンペラーはそもそマエストーソ(雄大に)の指示でも不気味さを表現したものでした。ただ、このラトルとロンドン響はおとなしく、まろやかにハーモニーを作っていきます。
チェリビダッケとかのを聴いているとゆったりとしたテンポでブルックナーのスコアから色んな引き出しを出してくれるものなのですが、このラトルのは何だか淡白だなぁと思いながら聴き進めていると、トラック1の14分30秒あたりから始まるコーダでティンパニが狂気的な乱れ打ちをおこない、ようやくラトルらしい遊び心が出てきました。
第2楽章は、交響曲第5番の緩徐楽章と並んでブルックナーの中で最も美しい曲の一つですが、メランコリーさもあります。第1主題のオーボエによる憂いのある旋律を際立たせる解釈が私は好きなのですが、ラトルはあまり感傷的に浸ることはなく割りと淡々と流していきます。ここでもまろやかさとしなやかさがあるハーモニーですが。
第3楽章のスケルツォも伸びやかですが、ロンドン響にしてはあまり重厚にさせていません。第4楽章はこの交響曲の中で最も素晴らしい演奏だと思いました。しなやかさがあり、美しさが際立っています。
まとめ
ラトルがロンドン響と取り組むブルックナー・チクルスの第1弾。2015年に出た最新のコールス版を使ったスコアで、伝統に縛られない新たなブルックナー像を描いています。ただ、ブルックナー・ファンには物足りがあるかも。
オススメ度
指揮:サー・サイモン・ラトル
ロンドン交響楽団
録音:2019年1月13, 20日, バービカン・ホール(ライヴ)
スポンサーリンク
試聴
Apple Music で試聴可能。
受賞
特に無し。











コメントはまだありません。この記事の最初のコメントを付けてみませんか?