このアルバムの3つのポイント
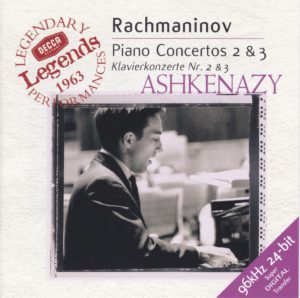
- アシュケナージのデッカデビュー盤
- 第2番はコンドラシン&モスクワフィルの好サポート
- ピアノ協奏曲第3番では後年と違うカデンツァを演奏
ヴラディーミル・アシュケナージのデッカ・デビュー
旧ソ連出身のヴラディーミル・アシュケナージは、1962年のチャイコフスキー国際コンクールでジョン・オグドンと優勝を分け合った後、デッカ・レーベルの専属となり、1963年3月のラフマニノフのピアノ協奏曲第3番でレコーディング・デビューを飾りました。そのときの指揮はアナトール・フィストゥラーリ、オーケストラはロンドン交響楽団でした。そして翌4月にはチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番をロリン・マゼール指揮のロンドン響(FC2ブログ記事)も録音しました。
さらに9月から10月に掛けては同じくラフマニノフのピアノ協奏曲第2番をキリル・コンドラシン指揮のモスクワ・フィルハーモニー管弦楽団と録音しています。デビュー年からロシア音楽の王道というべき難易度の高いピアノ協奏曲に挑んでいます。
ラフマニノフの第一人者、アシュケナージ
同じソ連出身ということもあり、ラフマニノフ演奏の第一人者というべきアシュケナージは、ピアニストとして、そして指揮者として、ピアノ作品、コンチェルト、管弦楽、室内楽まで、ありとあらゆる作品を演奏、そして録音をおこなってきました。2012年3月に録音されたラフマニノフ・レア作品集でも、珍しいピアノ小品を取り上げ、75歳という年を感じさせないぐらい、驚異的な開拓活動をしていました。
今回紹介するのは、アシュケナージにとってキャリア初期にあたる1963年のラフマニノフの2曲のピアノ協奏曲の録音。私が所有しているCD (1999年リリースのLegendsシリーズPOCL-6009)では第2番、第3番のトラック順になっているが、ここでは演奏順と同じ第3番、第2番の順で紹介していきます。
フィストゥラーリとのラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番
ピアノ協奏曲第3番ニ短調Op.30はウクライナ出身でイギリスの指揮者だったフィストゥラーリとロンドン響と1963年3月に録音したもの。まず、驚くのがその音質。購入したのは1999年の古いCDでしたが、それでも60年代の録音がこれほどクリアに聴こえることにびっくりしました。さすがデッカが誇る録音技術だと感心したものです。
アシュケナージはこのピアノ協奏曲第3番を、ピアニストとして5回、指揮者としても数回録音をおこなっていて、まさに十八番と言える作品。その最初となったのがこの1963年3月にロンドンのウォルサムストウで録音されたもので、まだ25歳の若かりしアシュケナージのみずみずしい演奏が聴けます。
冒頭はゆっくりとしたテンポで丁寧に演奏していますが、技巧的には申し分ないのにそれを前面に出そうとはせずに、オーケストラのハーモニーと溶け合おうとしているアシュケナージの姿勢に驚かされます。このラフマニノフのピアノ協奏曲第3番はピアニスト泣かせの難曲ですが、アシュケナージはそれを物ともせずに、自然な音楽を聴かせてくれます。デビュー盤とは思えない完成度です。
第1楽章のカデンツァは2種類ありますが、このときのアシュケナージは明るく軽快なほうを選んでいます。その後の再録音では重厚的なほうのカデンツァを選んでいて作品に迫力と重々しさを加えていたのですが、この1963年の録音では、軽やかでみずみずしいカデンツァの魅力。細かい音符のフレーズでのさざ波のような弾き方も格別にうまいです。
指揮のフィストゥラーリはこの録音以外で聴いたことがないのですが、ロンドン響から輝かしいサウンドを引き出しています。ベルリンやウィーンとも違う現代的な響きで、ややメランコリーを感じさせる響き。またトランペットなどの金管が鮮やかな差し色を出しています。
若干気になるのは、音声が途切れるところが何箇所かあるところ。リマスターがうまくいっていないのでしょうか。この録音の新しいリリースだと改善されているのかもしれないが、未検証です。
コンドラシンとのラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番
ピアノ協奏曲第2番ハ短調Op.18はコンドラシン指揮のモスクワフィルと1963年の9月から10月にかけて録音したもの。先程の第3番よりも印象に残るのがこの第2番のほうで、イギリスのグラモフォン誌でも下記のように絶賛されています。
アシュケナージの弾く協奏曲第2番の導入部は素晴らしかった―よく考え抜かれ、威厳に満ちていた。…彼のテクニックは全く比類の無いもので、だからこそアシュケナージがあくまでも音楽を尊重していることは、賞賛に値すると言わなければならない。
確かに聴いてみると冒頭の入りがかなり印象的です。アシュケナージは自分でも語っていましたが手がそれほど大きくないので、この協奏曲の冒頭のオクターブを遥かに超える和音を一度には掴めないのです。だからアルペジオ(分散和音)にして弾いているのですが、これは1971年〜1971年のアンドレ・プレヴィンとの録音、1984年のベルナルト・ハイティンクとの録音でも同じアプローチです。
ただ、この1963年の録音では、分散和音が滑らかにつながり、徐々にクレッシェンドをしながら弾かれているのが特徴的で、アルペジオにすることによって一度で打鍵した場合と比べて音の厚みが膨らみ、まるで鐘が鳴るかのように聴こえるのです。それでいて、オーケストラが加わるところではピアノの音量を小さくし、楽譜のp(ピアノ、弱く)の指示に従っているのです。
録音場所がロンドンなのに、ロンドン響ではなくモスクワフィルが演奏しているのか気になって調べてみたのですが、ナクソスのカタログでようやくヒントを見つけました。1963年9月にモスクワ・フィルはロンドン公演に出ていたのです。ヴァイオリンのダヴィッド・オイストラフとともに1963年9月19日にコンドラシン指揮、28日にユーディ・メニューイン指揮でロイヤル・フェスティバル・ホールで演奏していました。だから、コンドラシンもモスクワフィルもロンドンにいたのですね。
ただ、コンドラシン&モスクワフィルのコンビによる演奏のおかげで、ロシアらしい哀愁と暗さが引き立ち、このピアノ協奏曲第2番の数ある録音の中でも格別のものになっています。
アシュケナージはこの曲を後に何回も再録音しているが、モダンなロンドン響とプレヴィンとの演奏、くすみのあるような渋さがあるハイティンクとロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団との演奏とも違い、このモスクワフィルとはメランコリーなロシアさが出た演奏になっています。
まとめ
約60年前の録音だが、今聴いてもデッカが誇るサウンドであり、音質も良くクリアに聴こえます。特に第2番は一度は聴いてほしい名演。
オススメ度
ピアノ:ヴラディーミル・アシュケナージ
指揮:キリル・コンドラシン(第2番)
モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団(第2番)
指揮:アナトール・フィストゥラーリ(第3番)
ロンドン交響楽団(第3番)
録音:1963年3月(第3番), 1963年9月-10月(第2番), ウォルサムストウ・アセンブリー・ホール
スポンサーリンク
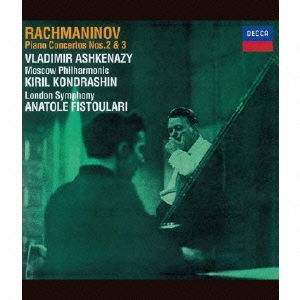
試聴
iTunesで試聴可能。
受賞
特に無し。1963年米国グラミー賞「BEST CLASSICAL PERFORMANCE – INSTRUMENTAL SOLOIST OR SOLOISTS (WITH ORCHESTRA)」にピアノ協奏曲第3番のレコードがノミネートしたが受賞ならず。




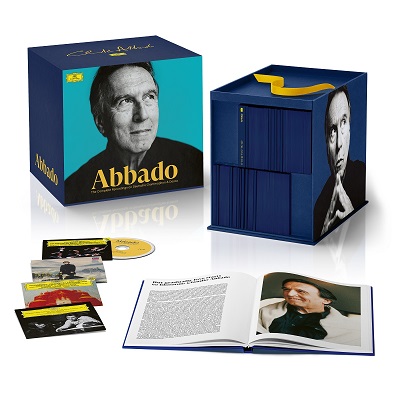


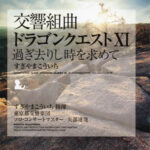
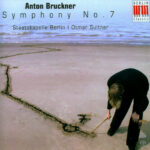
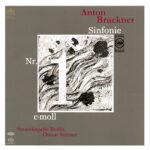
コメントはまだありません。この記事の最初のコメントを付けてみませんか?